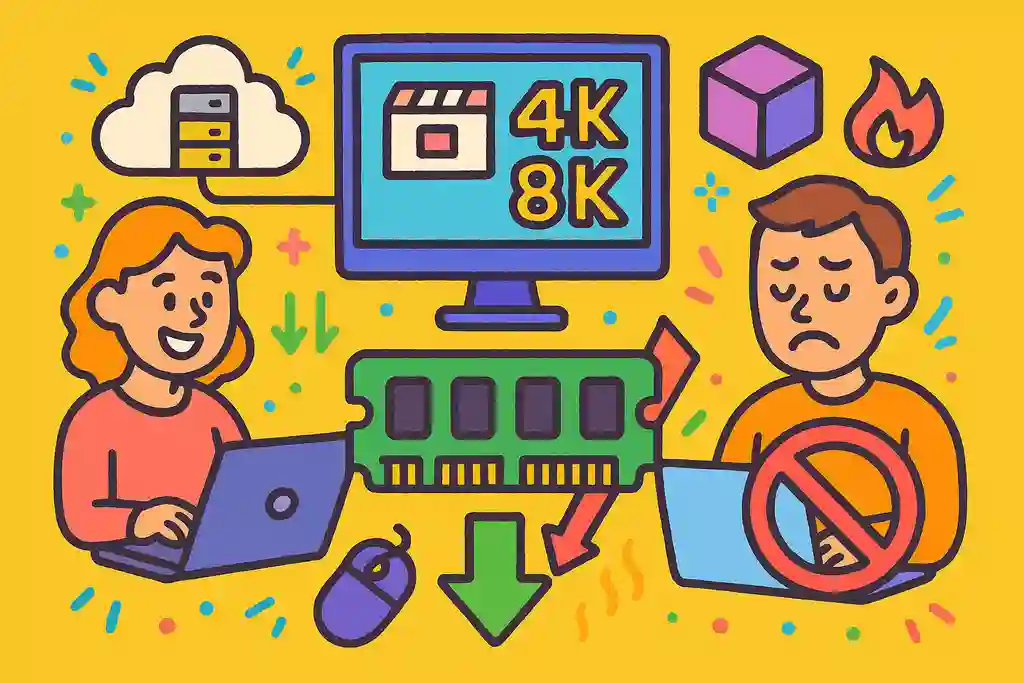
パソコンの性能を大きく左右する要素の一つが「メモリ」です。中でも128GBという大容量メモリは、一般的な構成と比べて圧倒的なスペックを誇りますが、その使い道や必要性について疑問を持つ人も少なくありません。
特に「メモリ 128gb 使い道」と検索している方は、ゲームや動画編集などの重い作業にどのような影響があるのか、パソコンへの導入が本当に適しているのかを知りたいはずです。
本記事では、ノートパソコンやデスクトップといったタイプ別の対応状況、1枚構成や2枚構成での違い、さらには「メモリ 多すぎ デメリット」とされる注意点にも触れながら、128GBメモリの現実的な使い道を詳しく解説していきます。
導入前に知っておきたいデメリットや、特定の用途においてどのように動画編集 メモリ 128gbが活かされるかを理解することで、無駄な投資を防ぎ、より効果的なPC構成が見えてくるはずです。
この記事のポイント
- 128GBメモリが必要な作業や用途がわかる
- ゲームや動画編集での実用性が理解できる
- 過剰なメモリ搭載によるデメリットを把握できる
- ノートパソコンやデスクトップの対応状況を確認できる
メモリ128GBの使い道は専門的な作業向け?
ゲームに128GBのメモリは必要なのか?

多くのゲームユーザーにとって、128GBのメモリは過剰なスペックです。
一般的なPCゲームの推奨スペックでは、16GB~32GB程度のメモリがあれば快適にプレイできます。
例えば、NECのガイドラインでは、ゲーミングPCのメモリ容量として16GBが推奨されています。
ゲーミングPCに必要なメモリは何GB?ストレージとの違いも解説
近年登場したハイエンドなAAAタイトルでも、64GBを必要とするケースはまれであり、128GBが必須となる場面はほとんど存在しません。
その理由は、ゲームそのものが使用するメモリ量には上限があるためです。
ゲームプレイ中に高画質設定を使い、録画や配信を同時に行う場合でも、実際のメモリ使用量は40GB〜50GB程度にとどまることが多いです。
例えば、「Microsoft Flight Simulator」のような重たいゲームや、MODを多用する「Skyrim」や「Cities: Skylines」などであっても、64GBで十分とされています。
ただし、複数のゲームを同時に起動したり、仮想マシン上でプレイするような特殊な使い方をする場合には、128GBが無駄になるとは言い切れません。
とはいえ、通常のゲーミング用途だけを目的とするのであれば、128GBのメモリを搭載する必要性はほとんどなく、コストパフォーマンスも悪くなります。
高性能なグラフィックカードやCPUに予算を割いた方が、ゲーム体験の向上につながるでしょう。
動画編集でメモリ128GBが活きる場面
動画編集において、128GBのメモリが本領を発揮する場面はたしかに存在します。
特に、4K以上の高解像度素材を扱うプロフェッショナルな現場や、長時間のマルチカム編集、大量のエフェクトやカラーグレーディングを同時に適用する作業では、大容量メモリが処理の安定性とスピードに直結します。
例えば、Adobe Premiere ProやDaVinci Resolveなどの編集ソフトは、素材を一時的にメモリ上に展開するため、大量のクリップを扱うと急激にメモリを消費します。
Adobeの公式サイトによれば、4K以上の動画編集の場合、32GB以上のRAMが推奨されています。→Adobe Premiere Pro 必要システム構成
これが64GBでも不足することもあり、特に作業中のタイムラインが複雑になるほど、128GBを搭載するメリットが明確になります。
また、レンダリング中やエクスポート処理の際にもメモリは多く使われ、十分な容量があれば処理が途中で止まることなく、快適に完了する可能性が高まります。
一方で、YouTube用の短めの動画や、フルHDの編集作業であれば、32GB~64GBのメモリで十分な場合がほとんどです。
つまり、128GBはハイエンドな制作環境や、将来的な負荷増加を見越した構成に向いていると言えるでしょう。
パソコンに128GBメモリを搭載する意味

128GBのメモリをパソコンに搭載することには、特定の用途において大きな意味があります。
特に、複数のメモリ集約型作業を並行して行う人や、サーバー用途・仮想マシンの運用・高精度なシミュレーション作業などに取り組むユーザーにとって、128GBのメモリは安定性と効率の向上につながります。
これには理由があります。
通常の作業では一つのソフトが使えるメモリ量には限度がありますが、複数のアプリケーションを同時に稼働させる場合、それぞれが大容量のメモリを要求するため、合計で128GB近くになることも珍しくありません。
例えば、仮想環境でWindowsやLinuxをいくつも同時に起動し、それぞれに開発環境や検証環境を構築する場合、32GBや64GBでは足りないケースもあります。
Windows 11 Proでは、最大2TBのメモリをサポートしており、高度な仮想化環境にも対応可能です。→Windows 11 の仕様とシステム要件
また、AI開発や大規模な3DCG制作、CADを用いた重い設計作業でも同様に高メモリが求められます。
ただし、こうした用途に該当しない一般的なユーザーが128GBを搭載しても、その性能を十分に活かすことは難しく、コストに見合った価値を得るのは困難です。
このように考えると、128GBのメモリは必要な作業を明確に把握した上で、初めて意味のある投資になると言えるでしょう。
無駄に大容量のメモリを積むよりも、目的に合った最適な構成を選ぶことが大切です。
ノートパソコンで128GBメモリは使える?
ノートパソコンで128GBのメモリを使うことは可能ですが、機種を慎重に選ぶ必要があります。
まず前提として、多くの一般的なノートパソコンは最大32GB、上位モデルでも64GBまでしか対応していません。
128GBという大容量メモリは、特殊なハイエンドモデルか、ワークステーション向けのノートでなければ対応できない構成です。
例えば、Lenovoの「ThinkPad Pシリーズ」や、HPの「ZBookシリーズ」などのプロ向けモバイルワークステーションであれば、最大128GBメモリをサポートする機種も存在します。
これらの機種は、メモリスロットを4つ搭載していたり、32GBのSO-DIMM(ノート用メモリ)を4枚挿入可能な設計になっています。
ただし、これらのモデルは高価で、一般ユーザー向けではありません。
加えて、消費電力や発熱量も増えるため、バッテリー駆動時間が短くなるといったデメリットもあります。
そのため、ノートパソコンに128GBのメモリを積みたい場合は、用途が非常に明確であることが前提となります。
仮想マシンを多数動かす開発者や、大量の高解像度映像編集を出先でも行う必要がある映像クリエイターであれば、選択肢のひとつになるでしょう。
つまり、128GBメモリをノートパソコンで使いたい場合は、対応機種の確認が最重要です。
事前にスペック表をしっかりチェックし、メモリの上限やスロット数を把握することが欠かせません。
メモリ2枚構成と4枚構成の違いとは
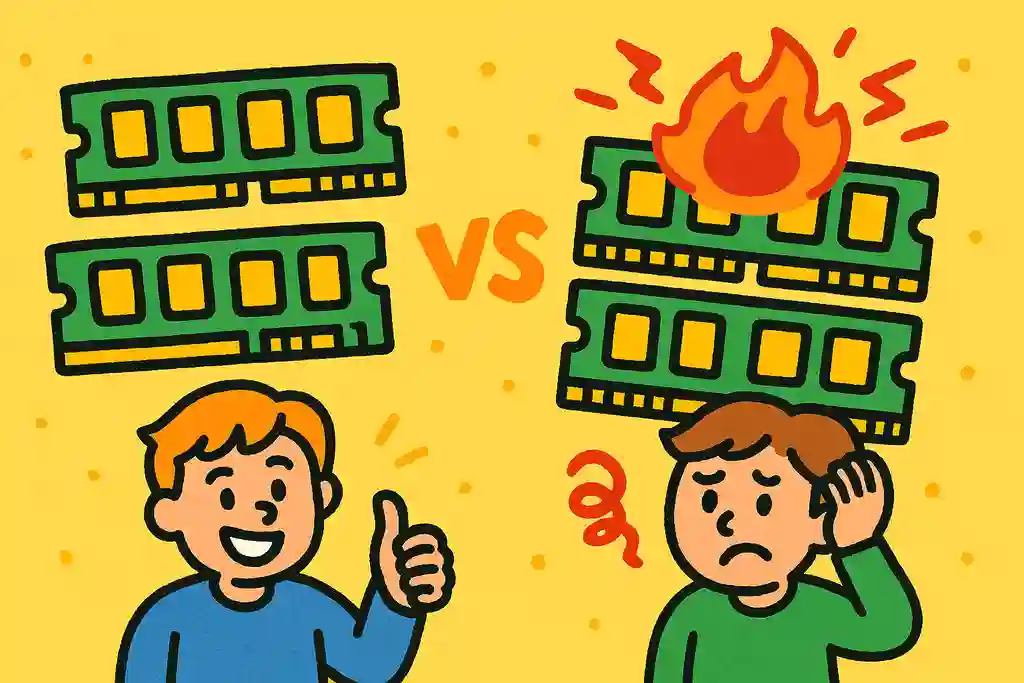
メモリの枚数による構成の違いは、PCの性能や安定性に影響を与える重要な要素です。
一般的なPCでは、2枚もしくは4枚のメモリモジュールを使って構成されることが多く、それぞれにメリットとデメリットがあります。
まず、2枚構成の場合は「デュアルチャネル」と呼ばれる仕組みに対応でき、メモリの転送速度が向上します。
例えば、16GB×2枚で32GB構成にすることで、よりスムーズな動作を実現できます。
多くの一般ユーザーやゲーマーにとっては、この2枚構成が最もバランスが良く、コスト面でも合理的です。
一方、4枚構成では「クアッドチャネル」に対応するマザーボードであれば、さらに高速なメモリ転送が可能になります。
ただし、実際にクアッドチャネルに対応しているのはハイエンドのデスクトップやワークステーション向けのモデルに限られます。
また、全スロットにメモリを挿すことで発熱が増加し、安定性に影響が出る場合もあるため、冷却性能にも注意が必要です。
例えば、128GBのメモリを搭載する場合、32GB×4枚の構成が一般的です。これにより合計容量を確保しつつ、クアッドチャネルを活かせる設計になります。
【セット購入におすすめ】安定動作が期待できる4枚組セットはこちら → Kingston DDR4 32GB×4枚 メモリキット
ただし、メモリ4枚構成はシステムへの負荷も高くなりやすいため、マザーボードや電源の品質も重要になります。
相性問題も発生しやすくなるため、同一メーカー・同一モデルのメモリを揃えることが基本です。
このように、2枚構成と4枚構成にはそれぞれ特徴があり、用途やシステムに応じた最適な選択が求められます。
特に高負荷作業を想定する場合には、4枚構成のメリットを活かしつつ、安定性にも配慮したパーツ選びが重要になります。
メモリ128GBの使い道や注意点とデメリット
メモリが多すぎることで起きるデメリット

メモリが多ければ多いほど良いと考えがちですが、使い切れないほどの容量を搭載すると、かえって無駄になる場合があります。
まず、メモリを多く搭載することでコストが大幅に増加します。たとえば、16GBや32GBといった一般的な容量であれば価格も抑えられますが、128GBともなると非常に高価です。
用途に対してオーバースペックになれば、投資に見合ったパフォーマンスは得られません。
また、搭載できるメモリが多いということは、システム全体にかかる電力や発熱も増えることを意味します。
これにより、冷却性能が追いつかず、パフォーマンスが安定しないというトラブルが発生する可能性があります。
さらに、すべてのソフトウェアが大量のメモリを有効活用できるわけではありません。
軽作業や一般的なゲームプレイ、ネット閲覧が中心の用途であれば、16GB~32GBでも十分に快適です。
128GBまで必要とするのは、大量の仮想マシンを動かす開発者や、4K/8K動画のリアルタイム編集といった専門作業に限られます。
このように、メモリを多く積めば必ず性能が上がるとは限らず、むしろコストや熱の問題が増すこともあるため、必要な用途を明確にした上で、容量を選ぶことが大切です。
メモリ128GBを選ぶ際の注意点
メモリ128GBは非常に大容量で魅力的に感じられるかもしれませんが、選ぶ際にはいくつかの重要な注意点があります。
まず、対応しているマザーボードかどうかを必ず確認する必要があります。
一般的なマザーボードでは最大64GBまでしかサポートしていないことが多く、128GBに対応しているのは主にハイエンドまたはワークステーション向けのモデルです。
また、メモリスロットの数にも注意が必要です。128GBを実現するには、32GBのメモリモジュールを4枚、または16GBを8枚使うなど、構成によってスロット数が変わります。
スロットが足りなければ、物理的に搭載できないため意味がありません。
さらに、OSの制限も確認することが重要です。
WindowsのHomeエディションでは128GBに対応しておらず、ProやWorkstationエディションでなければ利用できない場合があります。
その上、メモリの相性問題も考慮する必要があります。
異なるメーカーや速度のメモリを混在させると、正常に動作しなかったり、性能が制限される可能性があります。できるだけ同一モデルで揃えることが推奨されます。
このような理由から、128GBのメモリを選ぶ際は、「対応マザーボード」「スロット構成」「OSの制限」「相性確認」といった複数の要素を事前に調査し、慎重にパーツ選びを行うことが重要です。
デスクトップ以外では非対応もある
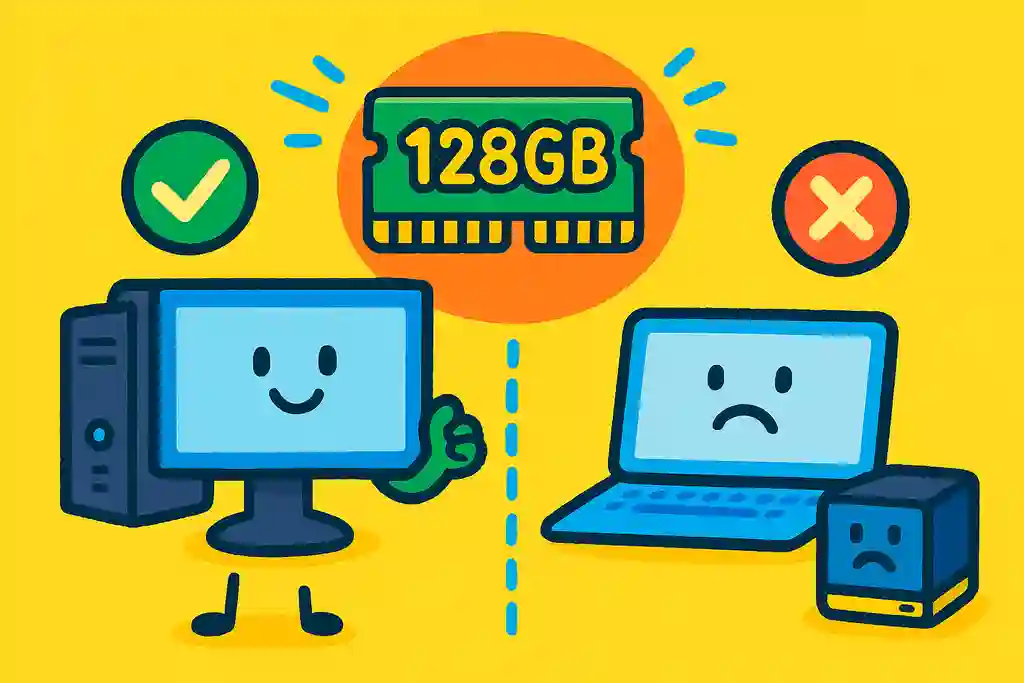
メモリ128GBのような大容量は、基本的にデスクトップPC向けの構成であり、それ以外のデバイスでは対応していないケースが多くあります。
特にノートパソコンやミニPC、タブレット端末では、物理的な構造上、メモリスロットが少なかったり、メモリがオンボード(取り外し不可)であるため、容量の拡張がそもそもできない設計になっていることが一般的です。
例えば、一般的なノートパソコンでは最大32GB、多くても64GBまでが上限となっており、128GBに対応しているモデルは一部のモバイルワークステーションに限られます。
それらの機種は特別なマザーボード構成や冷却設計を採用しているため、価格も高額になります。
また、省スペース性が重視されるミニPCでは、2スロットしか搭載していないこともあり、128GBのような大容量には到底対応できません。
タブレットや一体型PCに至っては、メモリ交換ができないケースも多く、そもそも選択肢に入りません。
このように、128GBメモリはデスクトップPC向けのスペックであり、それ以外のデバイスでは非対応であることが多いという点を理解しておく必要があります。
パソコンの購入やメモリ増設を検討する際には、対応可否を事前に調べてから選択することが失敗を避けるコツです。
1枚で128GBメモリは使えるのか
現在のパソコン環境において、1枚のメモリで128GBを使用することは可能ですが、条件が限られているため注意が必要です。
まず前提として、128GBのメモリモジュールは一般的な家庭用パソコンではほとんど対応していません。
通常のマザーボードでは、1スロットあたり最大32GBまたは64GBが上限であり、128GB単体のモジュールを使用できるのは、特定のワークステーションやサーバー向けのハイエンドマザーボードに限られます。
これには、Registered DIMM(RDIMM)やLoad Reduced DIMM(LRDIMM)といった、特殊なメモリ規格が関係しています。
これらの規格は、一般的なUnbuffered DIMM(UDIMM)とは互換性がなく、対応マザーボードや対応CPUでなければ正常に認識されません。
また、1枚128GBのメモリは非常に高価です。
購入価格も数万円から十数万円に達するため、コストパフォーマンスという観点でも、一般ユーザーが手軽に導入できる選択肢ではありません。
このような理由から、1枚のメモリで128GBを実現することは技術的には可能であるものの、利用には高度な知識と専用の環境が求められます。
個人ユーザーがパソコンに高容量メモリを導入する場合は、複数枚構成での合計128GBを検討する方が現実的です。
高容量メモリは誰に必要なのかを考える

128GBのような高容量メモリは、すべてのユーザーにとって必要なものではなく、特定の用途や職業に向けた構成です。
まず対象となるのは、大量のメモリを消費するプロフェッショナル用途です。
たとえば、4Kや8Kといった高解像度動画を扱う動画編集者、大規模な3Dモデルを扱うCGデザイナー、仮想マシンを複数同時に動かすシステムエンジニアなどが該当します。
こうした業務では、作業中に数十GB単位のメモリを使うことが一般的であり、余裕のある128GBを搭載することで快適なパフォーマンスを実現できます。
また、データサイエンスや機械学習など、高速処理とメモリ展開が要求される分野でも、高容量メモリの恩恵は大きいです。
膨大なデータセットを一括で読み込むような作業においては、128GBでもギリギリになる場合もあります。
一方で、一般的な用途――たとえばウェブ閲覧や動画視聴、資料作成、軽めのゲームなどでは、16GBから32GBもあれば十分です。
必要以上の容量は使われず、システム的にも余剰となってしまいます。
こうして考えると、高容量メモリが「誰に必要か」は明確です。それは、業務効率を高めたいプロフェッショナルや、処理負荷の高い作業に取り組むユーザーです。
そうでない場合は、適切な容量に抑える方が、コスト面でも無駄がありません。
メモリ128GBの使い道を総まとめで解説
- 一般的なゲーム用途では128GBは不要なスペック
- AAAゲームでも64GBあれば十分とされる
- 高解像度の動画編集では128GBが安定性と速度に直結する
- 長時間のマルチカム編集や大量エフェクト処理に効果を発揮
- 複数の仮想マシンを同時に動かす用途では有効
- 高精度シミュレーションやAI開発でも活用される
- ノートPCで128GBを使うには専用のハイエンド機種が必要
- モバイルワークステーションならノートでも対応可能な機種がある
- 2枚構成はコストと安定性のバランスに優れる
- 4枚構成は速度向上のメリットがあるが熱対策が必要
- 多すぎるメモリは無駄なコストや発熱増加を招く
- マザーボードやOSの対応状況を確認しないと非対応の可能性がある
- デスクトップ以外の機器では対応していないことが多い
- 1枚128GBのメモリは特殊規格で一般PCでは非対応が多い
- 必要な用途が明確でなければ高容量メモリは費用対効果が悪い
