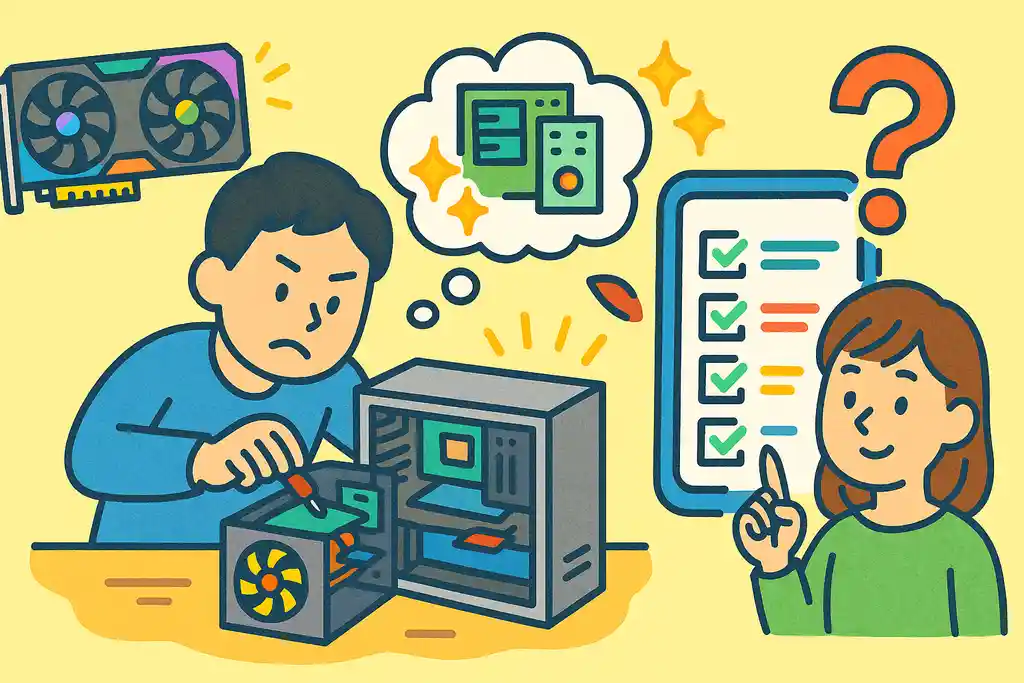
「自作pcやめとけ」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、きっと自作パソコンに興味があるけれど、本当に自分に向いているのか不安を感じているのではないでしょうか。SNSや掲示板、動画のコメント欄などで「自作PCはやめとけ」という声を目にすると、始める前から不安になってしまうのも無理はありません。
たしかに、自作PCには自由度やカスタマイズ性といった魅力がある一方で、パーツ選びの難しさやトラブル時の自己対応など、初心者にとってはハードルが高い側面もあります。「パーツの相性が合わなかったらどうしよう」「組み立てで失敗したら元も子もない」といった不安を抱えたままでは、安心してパソコン選びができません。
この記事では、自作pcやめとけと言われる理由をわかりやすく整理しながら、自作に向いている人・向いていない人の違いや、BTOパソコンとの比較、よくある失敗例や注意点まで幅広く解説しています。
読み終えたときには、自分にとって自作PCが本当に最適なのか、あるいは別の選択肢が良いのか、納得のいく判断ができるようになります。あなたの迷いを減らし、後悔しないパソコン選びのヒントが見つかるはずです。
この記事のポイント
- 自作PCがやめとけと言われる具体的な理由とその背景
- 初心者が失敗しやすいポイントや注意点
- 自作PCとBTOパソコンの違いとそれぞれの向き不向き
- 自作に向いているかどうかを判断するチェック基準
自作PCはやめとけと言われる理由と判断基準
自作PCはやめた方がいいのか?理由と判断基準を整理

自作PCは自由度が高い反面、パーツ選びやサポートの難しさから初心者にはハードルが高い面も。向き不向きを見極めることが大切です。
自作PCに興味があるけれど、「やめたほうがいい」と聞くと不安になりますよね。確かに、自作PCには魅力がありますが、誰にでもおすすめできるわけではありません。
まず自作PCでは、自分でパーツを選んで組み立てます。パーツにはたくさんの種類があり、組み合わせの相性もあります。間違った組み合わせをすると、動かなかったり壊れたりすることも。初心者にはこの選定作業がとても難しく感じられるでしょう。
次に、メーカー製パソコンと違い、トラブルが起きたときに「サポートしてくれる人」がいません。自分で原因を調べて、直さなければならないこともあります。さらに、初期不良や故障のときの対応もパーツごとになるため、面倒な手続きが増えることもあります。
また、思ったよりコストがかさむこともあります。「自作は安い」と言われますが、OSや工具、失敗時の買い直しまで考えると、BTOパソコンの方が安いこともあるのです。
とはいえ、「パーツ選びが楽しい」「自分好みにしたい」という人には向いています。大切なのは、自作に向いているかどうかを見極めること。不安が大きいなら、まずはBTOパソコンから始めるのも一つの方法です。
自作PCのメリット・デメリットを客観的に比較
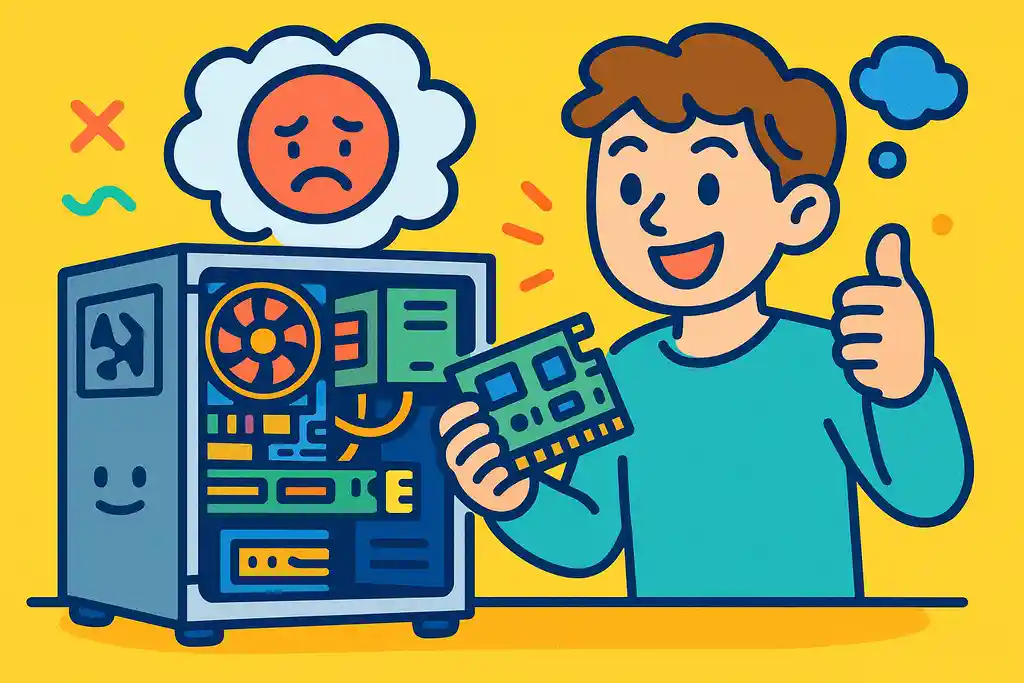
自作PCは自由度が高く長く使える反面、知識や対応力が求められるため、楽しめる人には向いているが初心者や手間を避けたい人には不向きです。
自作PCは「自分で選んだパーツで理想の1台を作れる」という自由さが最大の魅力です。必要な性能だけを重視したり、見た目にこだわったりできるため、パソコンをカスタマイズしたい人にはぴったりです。ゲーム、動画編集、配信など目的に合ったパーツ構成ができるのも大きな強みです。
さらに、あとからパーツを交換したり追加したりしやすいため、長く使いたい人にも向いています。たとえば、数年後にグラフィックボードだけ変えれば最新のゲームにも対応できる、という柔軟さがあります。
一方で、デメリットもあります。まず、すべてのパーツを自分で調べて選ぶ必要があり、時間と知識が必要です。初めての人にとっては、それだけで大きな負担になります。しかも、うまく組み立てられなかったり、動作しない原因を突き止めるのも自分の責任です。
また、トラブルが起きたときの保証やサポートは基本的にありません。メーカー製PCなら一括で対応してもらえますが、自作はパーツごとの対応になるため面倒です。
自作PCは、「自分で調べたり試したりするのが苦じゃない人」「パソコンを趣味として楽しめる人」には向いています。逆に、「とにかくすぐ使いたい人」「詳しい人が身近にいない人」にはあまりおすすめできません。
初心者が自作PCで失敗しやすいポイントとは?

初心者が自作PCで失敗しやすいのは、パーツの相性や接続ミス、バランスの悪い構成によるもの。トラブル時の対処も難しく、事前準備が重要です。
自作PCに挑戦した初心者がよく失敗してしまうのは、パーツ選びや組み立ての知識が不十分なまま進めてしまうことです。特に最初は、「これだけで動くと思ったのに…」というトラブルが多くあります。
たとえば、「マザーボードとCPUのソケットが合っていない」「メモリの規格が違う」「電源の容量が足りない」など、パーツ同士の相性問題が失敗の原因になります。また、ケーブルの接続を間違える、ネジの締めすぎでパーツを壊すなど、物理的なミスも少なくありません。
ASUS公式サイトでは、CPUの取り付け方法やソケットの確認手順が詳しく解説されています。
構成を考えるときに、「とにかく高性能なパーツを集めればいい」と思いがちですが、それでは予算を超えたり、電力や冷却のバランスが崩れてトラブルにつながります。性能のバランスを考えない構成も、初心者に多い失敗です。
さらに、自作PCは起動しないときのトラブル対応が難関です。「どこが悪いのか」を一つずつチェックしていく必要があり、これに時間もストレスもかかります。部品に問題があっても、どれが原因か分からず、最悪すべてを買い直す羽目になることも。
こうした失敗を防ぐには、事前にしっかり調べる、信頼できる構成例を参考にする、サポートのあるショップで購入するなどの工夫が大切です。
自作PCとBTOパソコンのコスト・性能比較

自作PCは自由度が高く安くできる可能性があるが、手間や知識が必要。BTOは安心で手軽なうえ、性能も十分でコスパも高い選択肢。
| 項目 | 自作PC | BTOパソコン |
|---|---|---|
| コスト | パーツを選べば安くできることも。ただし見えないコストが発生することがある | 安定しているが、場合によっては高めに感じることがある |
| カスタマイズ性 | 自由に構成ができ、自分好みにできる | 限られた選択肢から選ぶことになる |
| 組み立て | 自分で組み立てる手間が必要。失敗のリスクもある | 組み立て不要で、すぐに使用できる |
| サポート | パーツごとに保証があるが、サポートは自分で行わなければならない | 一括サポートが受けられるので、トラブル時に安心 |
| パフォーマンス | パーツの選び方によっては非常に高性能にできる | 高性能モデルも多く、ゲームや高負荷処理もこなせる |
| おすすめ対象 | カスタマイズを楽しみたい人、パソコンの知識がある人 | 手間を減らしたい人、安心して使いたい人 |
パソコンを買うとき、「自作PCの方が安い」とよく聞きますよね。でも、実は必ずしもそうとは限りません。自作とBTO(メーカーが組んでくれるパソコン)には、それぞれ得意なところとそうでないところがあります。
まず、自作PCのメリットは、パーツを自由に選べて、自分の好きな構成にできることです。上手く組めば、同じ性能でもBTOより安くなることがあります。特にグラフィックボードなどの高価なパーツを安く手に入れられれば、コストはぐっと下がります。
でも、自作には見えないコストもあります。OS代、工具、失敗したときの買い直し、そして何より時間と労力が必要です。また、パーツに問題があったときの対応も自分で行わなければなりません。
一方、BTOパソコンは、最初から動作確認された状態で届きます。組み立てや設定は不要で、すぐに使えます。サポートも一括して受けられるので、トラブル時にも安心です。価格も昔ほど高くなく、むしろ「コスパがいい」と感じることもあります。
ゲーム用パソコンが欲しい場合、BTOでもかなり高性能なモデルが用意されています。こだわりがなければ、BTOで十分です。
パソコンに慣れていて、「カスタマイズを楽しみたい」「作る工程が好き」という人は自作PC。手間を減らしたい、安心して使いたい人はBTOがおすすめです。
自作PCの見積もり・予算の考え方

自作PCは使い道を明確にしたうえでパーツを選ぶのが大切。予算オーバーしやすいので、用途に合った見積もりを心がけることが失敗を防ぐコツです。
自作PCを作るときにまず必要なのが「どれくらいお金がかかるのか?」を知ることです。何も考えずにパーツを選ぶと、気づけば予算オーバー…というのは初心者にありがちなミスです。
パソコンの用途によって必要なスペックが変わります。たとえば、ネット閲覧や書類作成がメインなら8万円前後でもOKです。ゲームや動画編集が目的なら15〜20万円以上かかることもあります。これにモニターやOS、キーボードなどを含めると、さらにプラスされます。
予算に合わせたパーツ選びには、AmazonのPCパーツセクションが参考になります。
見積もりのときは、まず「必要な用途」を決めてから、それに合うパーツを選びましょう。よくある失敗は「全部高性能にしておこう」として、使い切れないほど高いパーツを買ってしまうことです。無駄にお金を使わないためには、CPUとグラフィックボード(GPU)のバランスが特に大切です。
また、意外と見落とされやすいのが「OS代」や「ケースファン」「電源」などの小物類。細かいものも合計すると、最初の予想より1〜2万円高くなることも珍しくありません。
必要に応じて補強パーツを自作するのも手です。👉 グラボの支えを100均で作る安定支柱!安く安全に補強する方法
自作PCは、こだわりだすと予算がどんどん膨らみます。だからこそ、最初に「自分は何のためにPCを使うのか?」をはっきりさせることが、無駄のない見積もりへの近道です。
Microsoft公式サイトでは、Windows 11の購入方法や価格について詳しく案内されています。
自作PCはやめとけ?迷う人の不安と疑問を解消
自作PCに不安を感じる人が確認すべきチェックポイント

自作PCに不安がある人は、知識・対応力・時間の余裕があるかを確認することが大切。向き不向きを知ることで、安心して選ぶ判断ができます。
- パソコンの仕組みに興味があり、学ぶことに前向きである
- 説明書を読むのが苦ではなく、自分で調べるのが好き
- 小さなトラブルを「面倒」ではなく「経験」として楽しめる
- 起動しなかった場合も冷静に原因を探って解決できる
- 問題が起きてもすぐ人に頼らず、自分で対応しようと思える
- 作業に時間をかけることが苦ではなく、納期に追われていない
- 自作に必要なパーツ購入・トラブル対応に費やす余裕がある
- BTOパソコンより自由度やカスタマイズ性を重視している
- 自分で保証や修理の手配ができるだけの知識・行動力がある
- トラブル時に各メーカーへ個別に問い合わせる手間を許容できる
- 初心者であっても「挑戦してみたい」と感じる気持ちがある
- 自分に向いていないと感じたらBTOに切り替える柔軟性がある
このリストをもとに「YES」が多ければ自作PC向き、「NO」が多ければBTOを検討するとよい判断材料になります。
「自作PCはやめとけ」と聞いて、やってみたいけど怖い…そんなふうに迷っている人は少なくありません。でも、向いている人とそうでない人には特徴があります。それをチェックすることで、自分に合っているかどうかが見えてきます。
まず、パソコンの基本的な仕組みを理解したいと思えるか。もし「難しいのはイヤ」「説明書も読むのが面倒」と感じるなら、自作は向いていないかもしれません。一方、調べるのが好きだったり、少しのトラブルも「勉強になる」と楽しめる人は向いています。
次に、万が一うまく動かなかったときに冷静に対応できるか。自作PCは完成してもすぐに動かないことがあります。そんなときにあせらず、原因を一つずつ調べていけるかが重要です。「すぐ誰かに頼りたい」人には、BTOパソコンの方が安心です。
さらに、予算や時間に余裕があるかも大事なポイント。自作PCはパーツをそろえるだけでなく、トラブル対応や調整にも時間がかかることがあります。急ぎでパソコンが必要な人には向きません。
最後に、サポートや保証が分かれていることを理解しているか。自作PCはパーツごとに保証があるため、修理や交換もすべて自分で対応しなければなりません。
不安があるのは当然ですが、自分の性格や目的に合っているかを確認することで、後悔のない選択ができます。
ゲーミングPCに自作は最適か?BTOとの違いを比較
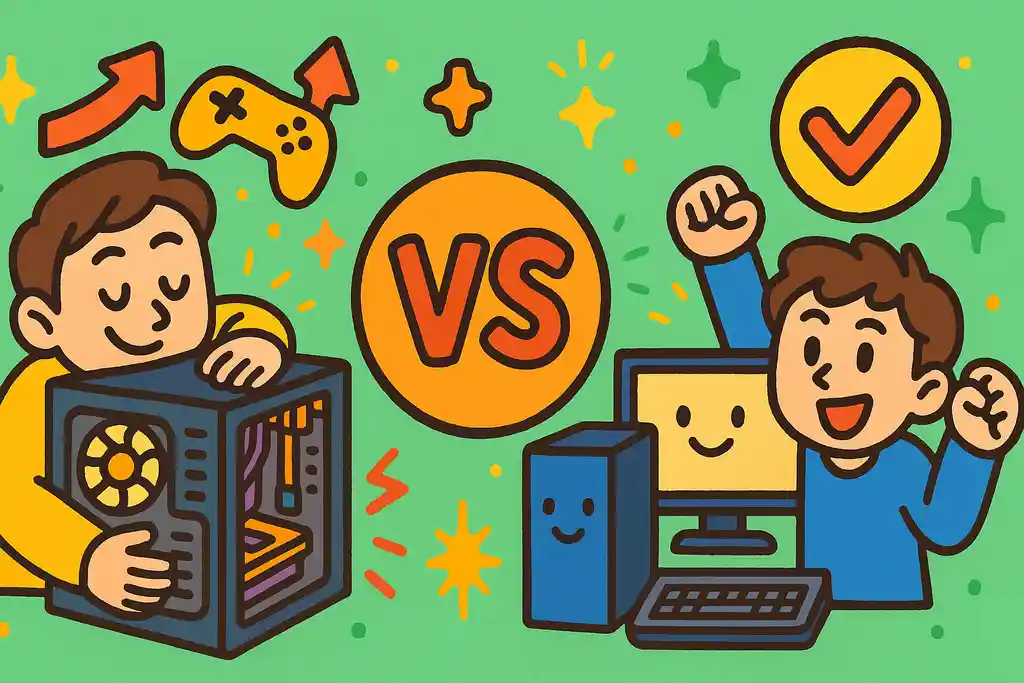
ゲーミングPCを自作すれば高性能な構成を安く実現できるが、BTOは安定性とサポートに優れる。こだわり重視なら自作、安心重視ならBTOがおすすめです。
| 項目 | 自作PC | BTOパソコン |
|---|---|---|
| コストパフォーマンス | パーツ選び次第で安く高性能にできる | 一部割高な場合もあるが構成は安定 |
| カスタマイズ性 | 自由にパーツを選べて理想の構成が可能 | ある程度決まった構成から選ぶ |
| トラブル対応 | 自分で原因を調べて対処が必要 | メーカーのサポートが一括で受けられる |
| 安定性 | パーツの相性によっては不安定なことも | 動作確認済みで届くため安心 |
| 組み立ての手間 | 自分で組む必要がある(初心者は要注意) | 完成品が届くのですぐ使える |
| おすすめタイプ | 自分で作るのが楽しい人、細かく調整したい人 | とにかく簡単・安心に使いたい人 |
ゲーム用のパソコンを選ぶとき、「自作とBTO、どっちがいいの?」と迷う人は多いですよね。それぞれにメリットがありますが、どちらが最適かは目的とこだわりの強さによって変わってきます。
まず、自作PCの大きな強みはパーツを自由に選べることです。グラフィックボード(GPU)や冷却ファン、ケースなど、好みに合わせて最強の構成を組むことができます。必要な機能だけに集中できるので、同じ予算でも高性能な構成にしやすく、コスパ重視派には魅力的です。
一方で、安定性やサポート面ではBTOに軍配が上がります。BTOパソコンは、販売前に動作確認がされているので、届いてすぐに使えます。パーツ同士の相性で動かない、という心配がほとんどありません。ゲームが快適に動くよう設計されたモデルも多く、初心者でも安心です。
特に【FRONTIER】のBTOパソコンは、高性能かつ国内生産で品質も安定しており、ゲーミング用途にもおすすめです。👉 FRONTIER公式サイトはこちら
また、BTOではメーカーのサポートがついているため、トラブルがあったときも相談しやすく、修理もスムーズ。自作ではパーツごとに問い合わせが必要になるため、手間がかかります。
「ゲームを最高の環境で楽しみたい」「見た目や性能にこだわりたい」人は自作がおすすめ。逆に「安定してすぐに使いたい」「失敗したくない」人にはBTOが向いています。
自作PCのトラブルとサポート面での注意点

自作PCはトラブル時のサポートがなく、原因調査や対応をすべて自分で行う必要がある。サポート体制を重視するならBTOが安心です。
自作PCは自由度が高い反面、トラブルが起きたときの対応はすべて自分でやる必要があるのが大きな特徴です。特に初めての人にとっては、ここが「やめとけ」と言われる理由の一つになっています。
まず知っておきたいのは、自作PCには一括サポートがありません。パーツごとにメーカーが異なるため、たとえば「電源がつかない」となった場合、原因がどの部品かを自分で調べなければいけません。しかも、パーツの不良であれば、それぞれのメーカーに個別に連絡して対応してもらう必要があります。
状況によっては、マザーボードのランプの色でトラブルの原因がわかることもあります。👉 マザーボードのランプが赤く光る原因と対処法まとめ
また、自作PCは初期トラブルが意外と多いです。配線ミスやBIOS設定の不備、パーツの相性問題など、些細なことでも起動しなくなることがあります。そのときに焦らず、順番に原因を調べられるスキルが求められます。
一方で、BTOパソコンやメーカー製PCは、購入先に相談すればまとめて対応してくれます。初心者にとっては、これはとても大きな安心材料になります。例えば、FRONTIERでは購入後のサポートや修理対応が充実しています。
自作PCに挑戦するなら、「何かあったとき、自分で調べて解決できるか?」を冷静に考えておくことが大切です。すぐに使いたい人や、サポート重視の人にはBTOの方が向いています。
自作PCのパーツ選びで起こりがちなミス

パーツ選びでは相性ミスや過剰スペック、電源不足などがよくある失敗。用途と予算を決めてから、対応パーツを確認して選ぶのが成功のコツです。
自作PCでよくあるトラブルの多くは、パーツ選びのミスから始まります。とくに初心者のうちは「いいと思って買ったのに使えなかった」ということがよくあるので、注意が必要です。
まずありがちなのが、パーツの相性ミスです。たとえば、CPUとマザーボードのソケットが合っていなかったり、メモリの規格が対応していなかったりすると、組み立てても起動しません。見た目は似ていても、ちょっとした違いで使えないことがあるのです。各パーツの詳細は、AmazonのPCパーツ一覧で確認できます。
次に多いのが、性能の過不足です。ゲーム用にハイスペックなGPUを選んだのに、CPUの性能が低くてボトルネックになったり、逆にネット閲覧程度しか使わないのに高価なパーツを選んでしまうなど、目的に合っていない構成が問題になります。
また、見落とされやすいのが電源容量です。必要な電力を満たしていないと、パソコンが途中で落ちたり、そもそも起動しなかったりします。電源は少し余裕を持ったものを選ぶのが安全です。
さらに、あれもこれもと高性能パーツを選びすぎて、気づけば予算を大幅にオーバーしてしまうのも初心者に多いパターンです。最初にしっかりと「何に使うのか」「予算はいくらか」を明確にしておくことがとても大切です。
自作PCは、計画と知識があれば楽しい作業です。正しい選び方を身につけることで、失敗のリスクを大きく減らせます。
グラボだけ交換したいときに他のパーツとの互換性を確認しないと、起動しなかったり性能を十分に発揮できないこともあります。 グラボだけ変えるなら要注意!互換性と交換方法を徹底解説
自作PCやめとけと言われる理由を総まとめ

- パーツ選びに知識と注意が必要で初心者には難しい
- 相性問題や接続ミスなど構成段階でのトラブルが起きやすい
- 保証やサポートがパーツごとで一括対応が受けられない
- 起動しないときの原因特定が複雑で時間がかかる
- トラブル時の対応がすべて自己責任になる
- 「安く作れる」は構成や時期によって成り立たないこともある
- OSや工具代など見えにくいコストが多く発生する
- パーツの価格変動で予算管理が難しい
- BTOパソコンの方が初期設定済みで安心して使える
- 自作は時間と労力を要するため忙しい人には不向き
- グラボやCPUなど高性能パーツの選び方に迷いやすい
- 自作に向いていない性格・環境の人も存在する
- 初心者は冷却・電力バランスなど細かい設計でつまずきやすい
- 自作の自由度は高いが失敗したときのリスクも比例して高い
- BTOでもゲーミングに十分対応できるモデルが多く存在する
