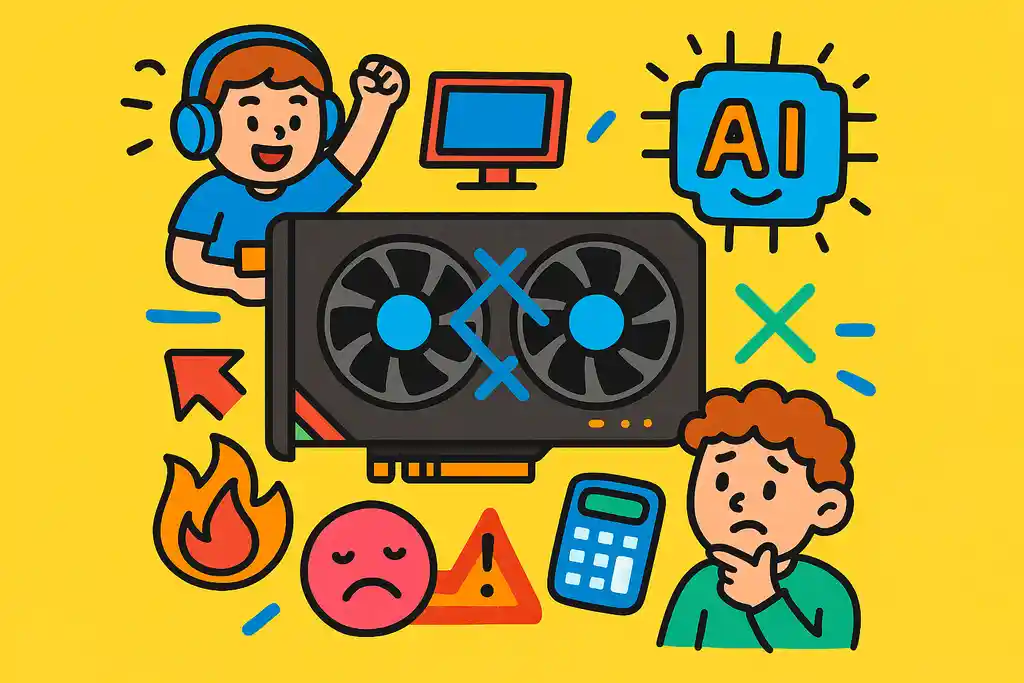
GPUを2枚搭載する「GPU2枚差し」という構成に興味がある方にとって、そのメリットや仕組みは非常に気になるポイントではないでしょうか。
特に、GPU2枚差しでゲームは快適になるのか、実際のメリットは何かを事前に理解しておくことで、失敗のないPC構築につながります。
このページでは、GPU2枚差しの基本的な構成や注意点、具体的な設定方法までやさしく解説していきます。
また、GPU2枚を使ったディープラーニングの活用方法や、GPU2枚差しで必要となるマザーボードの条件など、構成を検討するうえで知っておきたい情報も網羅しています。
さらに、GPU2枚差しの設定方法を具体的な手順とともに紹介し、LLM(大規模言語モデル)のような重たいAI処理にも活用できるかどうかにも触れています。
最近では、グラボ2枚を使い分ける独立運用や非SLI構成での実用性についても注目が集まっています。
グラボ2枚での負荷分散は本当に有効かという疑問に対しても、実例を交えながら丁寧に説明していきます。
この記事を読むことで、GPU2枚差しの構成があなたの用途にとって本当に有効かどうかを判断しやすくなり、後悔のない選択ができるようになります。
初めてGPUを2枚使う人にもわかりやすくまとめているので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
この記事のポイント
- GPU2枚差しによるゲームや作業環境でのメリットと注意点
- マザーボードや電源など構成に必要なハードウェアの条件
- 独立運用や非SLI構成でも活用できる具体的な使い道
- ディープラーニングやLLM用途におけるGPU2枚の効果と限界
GPUを2枚差すと何が変わる?基本と仕組みをやさしく解説
ゲームや作業が快適に?GPU2枚差しのメリットとは

GPUを2枚使うことで、ゲームや高負荷の作業がより快適に行えます。とくに高解像度やマルチディスプレイ環境で効果的ですが、対応ソフトでないと性能向上は望めない点に注意が必要です。
GPU(グラフィックボード)を2枚差しにすると、処理能力が大幅に向上し、ゲームやクリエイティブ作業がより快適になります。
一部のPCゲームや3Dレンダリング、映像編集ソフトなどでは、GPUの性能がパフォーマンスに直結します。
そのため、複数のGPUを組み合わせて処理能力を高めることで、よりスムーズな描画や高速な処理が可能になります。
とくに、4Kや8Kといった高解像度のゲームや映像編集では、1枚のGPUでは処理が追いつかない場面もあるため、2枚差し構成が真価を発揮します。
また、マルチディスプレイ環境でも、2枚のGPUがそれぞれの画面の処理を分担することで負荷を分散でき、安定した動作が期待できます。
ゲーミング用途においては、一部のタイトルがSLI(NVIDIA)やCrossFire(AMD)といった技術に対応しており、2枚のGPUが連携して描画処理を分担する仕組みも存在します。
ただし、すべてのソフトウェアが2枚差しの恩恵を受けられるわけではない点には注意が必要です。
非対応のアプリケーションでは性能向上が見られない場合もあるため、自分が使いたいソフトがマルチGPUに対応しているか事前に確認することが大切です。
GPUを2枚使うときに必要なマザーボードや構成の注意点
GPUを2枚使うには、複数スロット搭載かつ十分な電力供給ができるマザーボードと電源が必要です。加えて、スペースや冷却性能などハード面のバランスも考慮することが重要です。
GPUを2枚差すには、対応したマザーボードと十分な電力供給が可能な電源ユニットが必要になります。
まず、マザーボードには2つ以上のPCI Expressスロットが必要です。さらに、物理的にグラフィックボード2枚が干渉せずに設置できるスペースが確保されていることも重要です。
SLIやCrossFireを利用する場合は、それに対応したチップセットやBIOS設定も求められることがあります。
電源ユニットについても、2枚のGPUが動作するだけの出力が求められます。例えば、以下の高出力電源ユニットが適しています。👉Corsair RM1000x 1000W電源ユニット
たとえば、1枚あたり300Wを消費するGPUを2枚使う場合、600W以上の電力がGPUに必要になるため、システム全体で考えると850W以上の電源ユニットが現実的です。
また、電源ケーブルの種類と本数も確認しておきましょう。
冷却面も見逃せません。GPUが2枚あるとケース内の発熱が増えるため、空冷や水冷などの冷却対策を講じる必要があります。
加えて、ケース自体のエアフロー設計も考慮しなければ、温度上昇によってパフォーマンスが低下してしまうことがあります。
GPU2枚差しの設定方法とは?導入前に準備すべきこと

GPU2枚差しには、装着・電源接続・ドライバ設定・ソフト側の有効化といった工程が必要です。マルチGPU設定を有効にしても、対応していないソフトでは性能が上がらない点にも注意が必要です。
GPU2枚差しの構成を正しく動作させるためには、事前準備と正しい設定が欠かせません。
まず、GPUを取り付ける前に、マザーボードと電源が対応しているかを確認します。
次に、静電気に注意しながらGPUをそれぞれのPCIeスロットにしっかり装着します。その後、各GPUに必要な電源ケーブルを接続し、通電準備を整えます。
PCを起動したら、ドライバーのインストールとGPU制御ソフト(NVIDIAコントロールパネルやAMD Adrenalin)を立ち上げ、SLIやCrossFireの有効化を行います。
設定メニューから「マルチGPUの有効化」オプションを選択し、再起動すれば基本設定は完了です。
なお、SLIやCrossFireはドライバーバージョンによって表記が異なる場合もあるため、公式の案内に沿って進めるのが安全です。
さらに、OS側やソフトウェア側でマルチGPUが正しく認識されているかのチェックも欠かせません。
例えば、GPU-Zやタスクマネージャーで認識状況を確認することで、問題がないかを把握できます。
ただし、最近のゲームやアプリではSLIやCrossFire非対応のものも増えているため、2枚差しによる性能向上を目的とする場合は事前にそのソフトの対応状況を確認することが賢明です。
SLI非対応でも使える?グラボ2枚の独立運用について
SLI非対応でも、グラボ2枚を別々の作業に割り当てることで高いパフォーマンスが得られます。ゲーム配信やクリエイティブ用途など、複数の処理を同時に行いたい場面で有効です。
SLIやCrossFireに対応していない場合でも、グラボを2枚使う意味は十分にあります。
というのも、SLIのようにGPUを連携させなくても、それぞれのグラフィックボードを独立して動作させる「独立運用」という方法があります。
この方式では、例えば1枚目のGPUでゲームをプレイし、2枚目のGPUで動画のエンコードや配信、AI処理など別のタスクを担当させることが可能です。
こうした使い分けにより、システム全体の効率を高めることができます。
実際、ゲーム実況をしながら録画やライブ配信を行う場合、1枚のGPUにすべての処理を任せるとフレームレートが不安定になることがあります。
しかし、2枚目のGPUに配信やエンコード処理を任せることで、ゲームプレイ自体のパフォーマンスを維持しやすくなります。
また、クリエイター向けの用途では、1枚のGPUで映像プレビュー、もう1枚でレンダリングといった分担も可能です。
ただし、独立運用には注意点もあります。アプリ側が複数のGPUを正しく認識し、それぞれを目的に応じて使い分けられる必要があります。
特定のタスクにしかGPUを割り当てられないソフトでは、2枚目が遊んでしまうケースもあるため、事前にソフトの仕様を確認しておきましょう。
「グラボを2枚使うと意味ない」って本当?よくある誤解と真実

「グラボ2枚は無意味」というのは誤解です。用途によっては非常に有効であり、特に配信や高度な処理を並行して行う場合には、2枚構成の方が適しています。
「グラボを2枚使っても意味がない」という意見を目にすることがありますが、それは一部のケースに限った話です。正しく理解すれば、2枚差しにも十分なメリットがあります。
このような誤解の多くは、SLIやCrossFireによる連携がゲームやソフトに対応していない場合に、性能向上が見られないことから来ています。
確かに、すべてのソフトが2枚のGPUをうまく活用できるわけではありません。そのため「意味がない」と感じる方もいるのです。
しかし、前述のように独立運用による使い分けや、マルチディスプレイ環境での作業分担といった運用方法では、グラボ2枚の利点が十分に活かされます。
特に、ゲーミングと配信、またはAI処理や動画編集といった負荷の高い作業を並行して行う場合には、1枚では対応しきれないシーンも出てきます。
さらに、複数枚構成は仮想マシンのGPUパススルーや、開発用途の演算処理など、一般的なゲーミング用途を超えた分野で高く評価されています。
つまり、目的によっては「意味がない」どころか、「1枚では足りない」というケースも存在するのです。
ゲーム以外にも!GPU2枚差しが活躍するシーンとは
AIやディープラーニングでGPU2枚はどこまで効果がある?

AIやディープラーニングでは、GPUを2枚使うことで学習時間を大幅に短縮できます。ただし、適切なフレームワーク設定やPC構成が必要で、必ずしも単純な2倍効果が得られるわけではありません。
AIやディープラーニングにおいて、GPUを2枚搭載することで得られる効果は非常に大きく、用途によっては1枚とは比較にならないほどの処理能力を発揮します。
高性能なGPUとして、以下の製品が人気です。👉NVIDIA GeForce RTX 3090 グラフィックボード
AI開発やディープラーニングでは、大量のデータを扱うトレーニング作業や、複雑なモデルを高速で動かす必要があります。
このとき、GPUの数が処理スピードに直結するため、1枚より2枚、2枚より4枚というように、性能をスケールアップしやすいのが特徴です。
特にPyTorchやTensorFlowのようなライブラリは、複数GPUに対応しており、「データ並列処理」や「モデル並列処理」を利用することで効率良く学習を進めることができます。
たとえば、画像認識や自然言語処理といったタスクでは、1枚のGPUで数時間かかるトレーニングが、2枚にすることで半分近くまで短縮されることもあります。
ただし、これには前提条件があります。マルチGPU対応のフレームワークやコード構成が必要なほか、GPU同士の通信を行うNVLinkなどの帯域設計にも注意が必要です。
また、メモリ容量の合計が使えるわけではなく、基本的にはそれぞれのGPUに同じモデルを配置して並列処理を行います。
一方で、GPUを2枚使っても性能が2倍になるとは限らない点も注意が必要です。
ボトルネックとなるのは、CPUやメモリ、ディスクI/OなどGPU以外の部分も多いため、全体のバランスを考えた構成が求められます。
話題のLLMも快適動作?GPU2枚で性能を引き出すコツ
LLMを快適に使うにはGPU2枚構成が効果的です。モデル並列や補助ツールを活用することで、大規模モデルもスムーズに動作させることが可能ですが、ハード面の強化も必要です。
話題のLLM(大規模言語モデル)を快適に動作させたい場合、GPU2枚構成は非常に有効な手段となります。
特に、GPUメモリ容量や演算性能が求められるLLM環境においては、1枚だけでは動作させることすら難しいこともあるためです。
例えば、最近人気のあるLLMの多くは、推論(生成)時でもVRAMを20GB以上使用するケースがあり、GPU1枚構成ではスペック不足になりがちです。
しかし、GPUを2枚にすることで、モデルの分割読み込みやレイヤーの並列化が可能になり、メモリ制約を回避しつつ実行することができます。
これを「モデル並列化」といい、LLMの構造を複数GPUにまたがって配置し、連携して動かす方法です。
さらに、GPU2枚をフル活用するには、NVIDIAの「Multi-Process Service(MPS)」や、Hugging FaceのAccelerateライブラリなどを活用することで、複数プロセスや分散処理を効率化できます。
こうした工夫を組み合わせることで、大型モデルでもよりスムーズな推論やトレーニングが可能になります。
ただし、LLMのように計算資源を大量に消費する用途では、電源容量や冷却性能も重要なポイントになります。
GPU2枚を安定動作させるためには、1000W以上の電源と、高性能な冷却環境が必要になるケースも多いため、ハード面の準備も怠らないようにしましょう。
GPUを2枚使うと負荷分散できる?意外な落とし穴とは

GPUを2枚使えば負荷が自動的に分散されるわけではありません。アプリが対応していない場合は性能向上が見込めず、むしろ電力・発熱などの負担が増す可能性もあるため、目的に合った構成が重要です。
GPUを2枚使えば、単純に処理を半分ずつ分担して効率的に動作する――そう考える方は多いかもしれません。
しかし、実際にはそう簡単に負荷が分散されるとは限らず、期待したほどの効果が得られないケースもあります。
なぜなら、GPUの2枚差し(マルチGPU構成)が有効に機能するには、ソフトウェア側がそれに対応している必要があるからです。
例えば、ゲームやクリエイティブソフトの多くは、1枚のGPUで最適化されており、2枚使っても性能が向上しないことがあります。
とくにNVIDIAのSLIやAMDのCrossFireといった技術は、近年では多くのアプリで非対応、あるいはサポートが終了していることも多く、2枚のGPUが完全に独立して動作してしまうこともあります。
その結果、2枚目のGPUがほとんど動作せず、消費電力や発熱だけが増えるという残念な状況に陥ることもあります。
さらに、グラボ間で処理をやりとりするには一定の通信が必要であり、ボトルネックが生じることもあります。
とくにPCIeレーン数や帯域幅が不足していると、逆にパフォーマンスが低下することもあるため注意が必要です。
つまり、負荷分散の効果を十分に引き出すには、対応アプリやシステム構成をきちんと把握した上で、GPU2枚の使い道を明確にする必要があります。
GPU2枚差しで後悔しないために知っておくべきデメリット
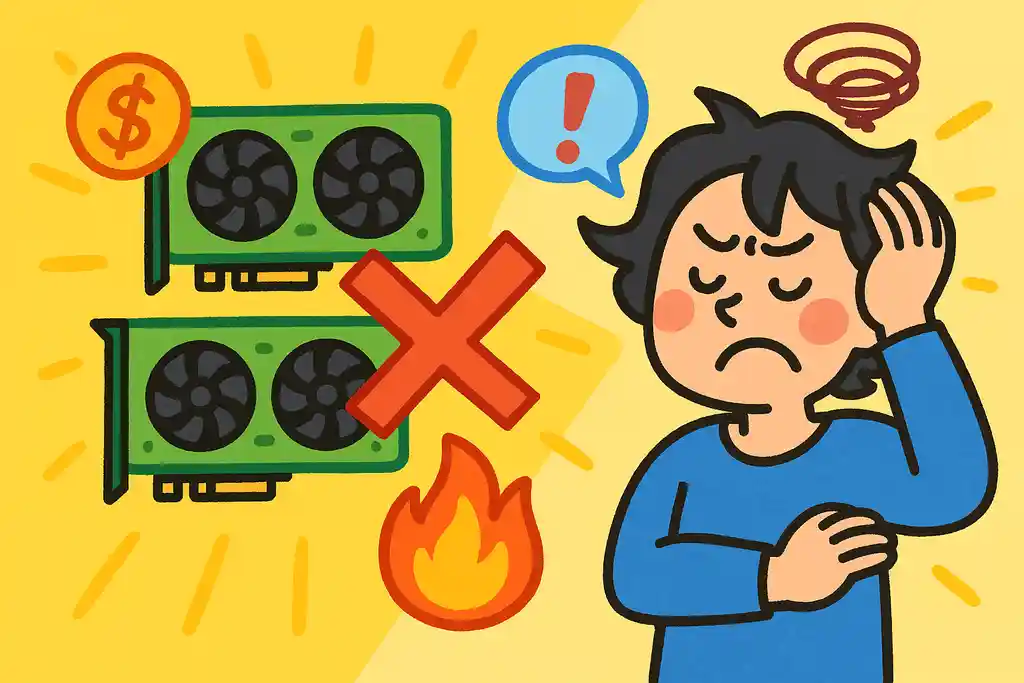
GPU2枚差しは高性能ですが、コスト増・発熱・アプリ非対応といったデメリットも大きく、十分な事前準備と知識がないと後悔する可能性が高くなります。
GPU2枚差しには確かに魅力的な側面もありますが、使いこなすにはそれなりの知識と準備が必要であり、事前に理解しておくべきデメリットも存在します。
まず最大の懸念点は、コストの高さです。同じ世代のGPUを2枚揃えるとなると、単純に費用は倍近くになります。
また、それに対応するマザーボード、電源ユニット、冷却システムもハイエンドなものが求められるため、全体の構成費用が大きく跳ね上がります。
次に、発熱と消費電力の問題があります。GPUは高負荷時に非常に熱を持ちますが、それが2枚になることでケース内の温度が大幅に上がることも珍しくありません。
その結果、ファンの騒音が増したり、他のパーツに悪影響が及ぶ可能性もあります。特に通気の悪いケースでは熱暴走や動作不安定につながるおそれもあるため、冷却設計は慎重に行う必要があります。
さらに、多くのゲームやアプリはマルチGPU非対応であり、2枚目のGPUが無駄になってしまうケースも少なくありません。
このため、「高性能=2枚差しが正解」と考えるのではなく、「自分が使うソフトがマルチGPU対応かどうか」をしっかり確認したうえで導入を検討すべきです。
このように、GPU2枚差しにはメリットもありますが、安易に手を出すと後悔する可能性も高い構成です。情報収集と計画的な構成が求められます。
GPU2枚差しの基本から応用までまとめてチェック
- gpu 2 枚 差しは高解像度やマルチディスプレイ環境で効果を発揮する
- ゲームや映像編集ソフトでは処理性能が大幅に向上することがある
- 使用するソフトがマルチGPUに対応していないと効果は限定的
- 対応マザーボードにはPCIeスロットが2本以上必要
- 電源ユニットは高出力かつ必要なコネクタ数を備えている必要がある
- ケース内部のスペースや冷却性能も構成時に重要な要素となる
- SLIやCrossFireによる連携動作にはドライバや設定が必要
- 独立運用すれば用途別にGPUを割り当てて使い分けできる
- ゲーム配信や録画、AI処理などの同時実行で威力を発揮する
- マルチGPUに対応していないソフトでは片方が遊ぶこともある
- AI・ディープラーニングでは学習時間を短縮できるケースがある
- LLMなど大規模モデルではモデル分割で2枚のGPUを活用可能
- ソフトによっては負荷分散が働かず、電力と発熱が無駄になる
- 導入には費用・発熱・騒音・構成の複雑さといったリスクもある
- 利用目的に合わせて対応ソフトや環境の確認が必要
